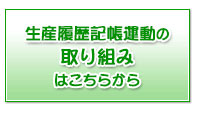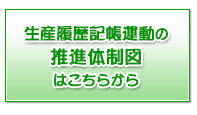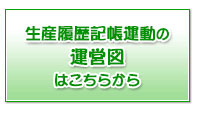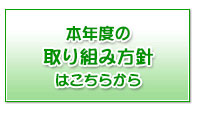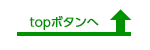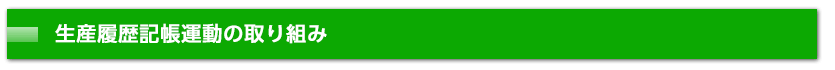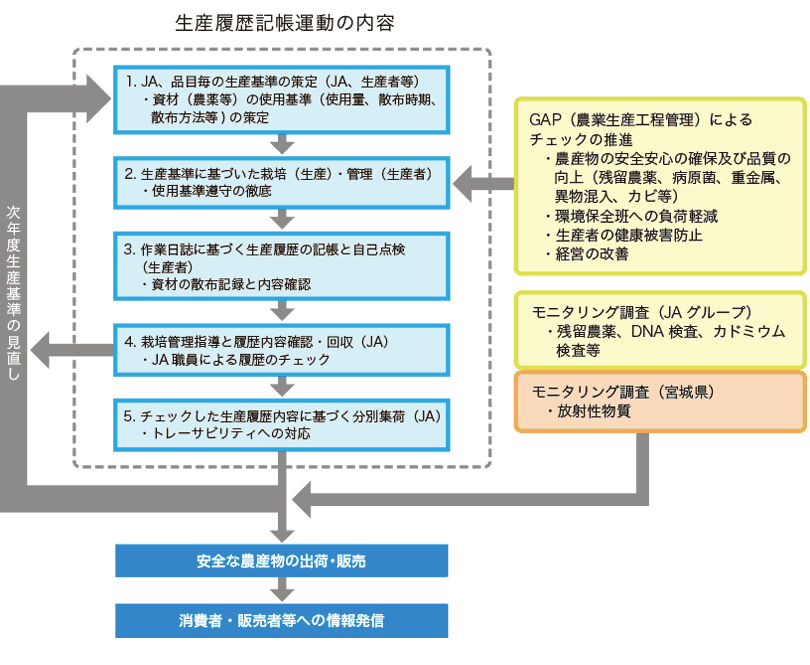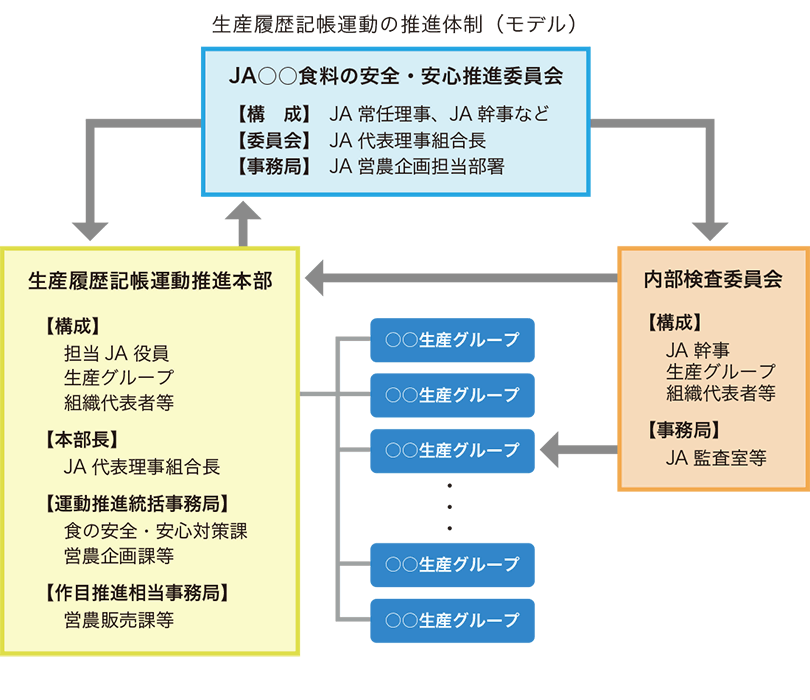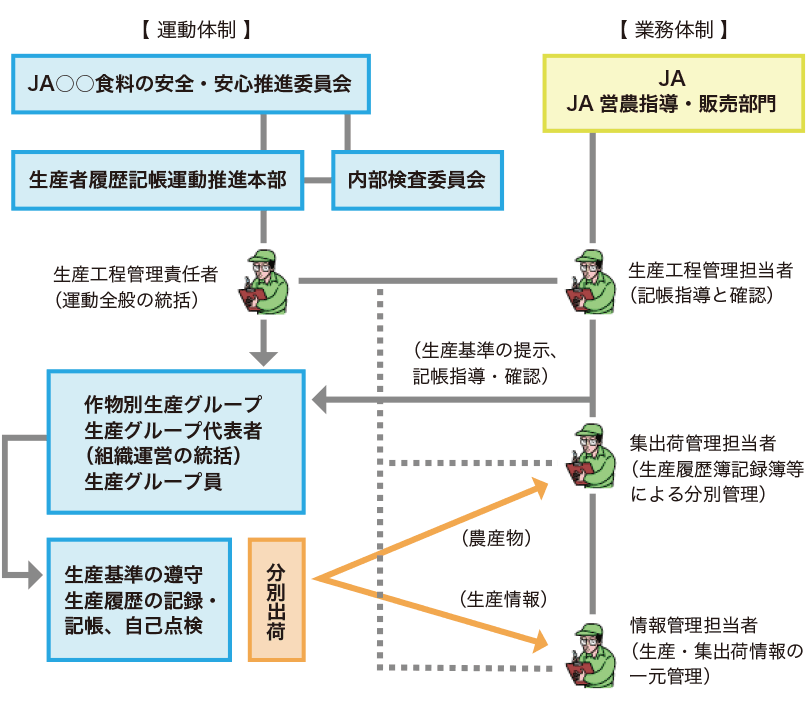JAグループ宮城の取り組み
安全・安心な「食」は宮城の大地から
-
JAグループ宮城では、農業者・消費者共通の願いである「安全・安心」な県内農産物の信頼性確保・徹底を図るため「生産履歴記帳運動」に県下あげて取り組んできました。さらに消費者へ安全な農畜産物を提供するため、生産段階の危害を回避する管理手法として「GAP」の導入を推進しております。
また「JAグループ宮城食品事業等信頼性向上自主行動計画」等JAグループ各段階における行動計画を策定し、食品業としての適切な衛生管理や食品表示の徹底を図り、食品の安全や品質を確保し消費者から信頼され続けるよう取り組んでおります。
JAグループ宮城食品事業等信頼性向上自主行動計画
-
JAグループ宮城は、食料の安定供給に取り組むことはもとより、食品(農畜産物)の安全や品質を確保し、消費者から信頼され続けるようにするため次の取り組みを徹底します。
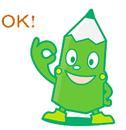
- コンプライアンス体制の構築の必要性について継続して周知徹底を図ります。
- 適正な衛生管理・品質管理を行うための取り組みの徹底を図ります。
- 表示の適正化に向けて必要な支援を行います。
- 生産履歴記帳の徹底とGAP(生産工程管理)手法の導入を進めます。
- 環境にやさしい農業を推進します。
- 消費者等に対して、JAグループとしての取り組み等について、ホームページなどを通じて提供します。
- 信頼性向上に向けた取り組みの中で明らかになってきた諸課題については、情報開示につとめ解決に向けて取り組みます。
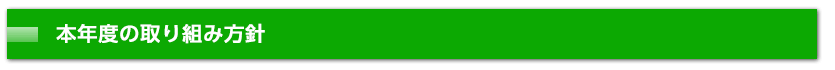
令和6年度「農産物の安全・安心」に関する取り組み方針について
令和6年6月11日
JAグループ宮城 食料安全・安心推進委員会
JA宮城中央会・JA全農みやぎ
- 1. 趣旨
-
JAグループ宮城は平成14年8月より食の安全・安心確保対策として「生産履歴記帳運動」を進めるとともに、記帳とGAP手法の導入推進等によりリスク管理の徹底を図ってきた。
一方、令和3年6月1日より、原則すべての食品等事業者は、HACCPを取り組むこととなったが、農業倉庫・カントリーエレベーター等については、原則としてHACCP制度化の対象外となり、「自主的な衛生管理」が求められている。
JAグループ宮城は引き続きリスク管理措置として、GAPやHACCPの導入推進等により、食の安全確保対策に取り組み、消費者への安全で安心な農畜産物を提供することに努める。 - 2. 重点取り組み事項
-
生産現場における食品表示等の関係法令遵守を基本に、生産履歴簿記帳の徹底、GAP・HACCPなどのリスク管理措置の導入推進を図る。また、農産物の放射性物質濃度の低減に係る技術対応について、国や県などの関係機関と連携・協力し、安全・安心な農産物の生産を振興するため、次の重点事項に取り組むこととする。
- (1) 食の安全確保対策の取り組みの強化
-
ア. 生産履歴簿の点検・確認・異物混入・異品種混入防止の徹底、玄米の残留農薬検査やDNA鑑定や米のカドミウム濃度検査
等を行い、その結果に応じ情報提供等を行う。
イ. 安全確保対策を担う、専門能力を備えた人材育成のための各種研修会、情報提供等を行う。 - (2) GAP手法導入対策
-
ア. JAグループ宮城におけるGAPへの基本的な考え方(平成29年6月制定)に基づき取り組みを進める。
イ. GAP手法導入を図るため、GAP総合研究所及び関係機関と連携し、JGAP指導員基礎研修会(8月6日〜7日:JA学園宮城)
を継続して開催する。
ウ. GH農場評価員養成講習、GLOBAL.G.A.P内部検査員講習会等の情報提供を行い、農産物におけるGAP手法導入の啓発・推 進を図る。 - (3) HACCPに沿った衛生管理導入への対応
-
農業倉庫・カントリーエレベーター等については、「自主的な衛生管理」が求められているため、自主的衛生管理の実行と保管米麦の品質保全とカビ防止・防虫・防鼠対策の徹底をはかり、米麦の保管管理に係る知識や技術の習得、品質・人身事故防止のための研修会の開催や巡回点検を行う。
・「宮城県JA農業倉庫担当者等研修会」(6月13日・JAビル宮城)
・「農業倉庫巡回点検」(7月実施予定) - (4) 放射性物質濃度低減対策の実施
- 農地土壌の放射性物質濃度の調査結果等から、平成30年4月宮城県が示した「宮城県産米の放射性物質吸収抑制対策について」にもとづき、宮城県米づくり推進本部を中心として、県段階及びJA・地域段階における推進体制のもと、必要な対策の推進を図る。
- 3. 確認事項
-
(1)この方針に定めのない事項については、委員長(中央会代表理事会長)が決定する。
なお、「重要案件」については、JAグループ宮城「食料安全・安心推進委員会」において、都度、決定するものとする。
(2)安全・安心確保に係る作物別の具体策等については、宮城県及び関係機関との連携・協議のもと全農県本部で策定する。
以上