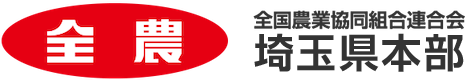営農についての情報
3月の麦の生育と管理 (2025年3月5日作成)
1.気象経過と麦の生育状況
気温は、1月下旬にやや高い時期があった以外、12月から2月下旬まで平年並みに経過し、ここ数年の暖冬と比べると寒い日が多くなりました。また、雨も2月5日に5mmを記録した後、3月3日まで降らず晴れて乾燥した日が続きました。
このため、小麦、大麦ともに生育は先月に続いて抑制気味に経過し、暖かかった前年と比べると11月播きで小麦は5日程度、大麦は10日程度遅れていますが、11月中に播種された麦は分げつも十分に確保され問題ありません。また、茎の伸長も始まり、大麦では間もなく茎立ちを迎えます。
一方、12月播きの生育は遅れ、特に中旬以降の播種で出芽が年を越して1月になった麦は草丈の伸長、分げつの発生とも少ない状態のままになっています。


2.今後の天候と予想される麦の生育
2月27日発表の1か月予報によれば、気温は、3月上旬は寒暖の変動が大きく、中旬は平年並み、下旬は平年並~やや高くなると予想され、降雨は平年並みからやや多い見込みです。
近年は3月の気温が非常に高く、麦は肥料切れの様相を呈しつつ茎立ちや出穂が早まる傾向が続いてきましたが、今年は極端な生育前進はなく、乾燥と低温で遅れていた肥効が発現し、11月播きの生育は平年並みに回復すると予想されます。
一方、12月播きは十分な生育量の確保ができず、遅発分げつの増加が懸念されます。
ビール大麦の茎立ちは11月中旬播きで3月5日、下旬播きで3月8日頃と予想され、小麦の茎立ちは、11月中旬播きで3月12日、下旬播きで3月16日頃と予想されます。
3.3月の管理作業
(1)追肥
ビール大麦にはこれ以上遅い追肥は控えましょう。特に12月播きは高たんぱく化と倒伏のリスクが高くなるので行わないで下さい。
小麦は、11月播きについては茎立ち前までに実施してください。しかし、12月播きは倒伏のリスク増加と硝子質粒の増加による外観の低下が懸念されるので、控えましょう。
(2)麦踏み
ビール麦は、11月播きは終了です。12月播きについては3月上旬のうちに倒伏軽減のために可能な限り実施しましょう。
小麦は、11月播きは3月上旬まで、12月播きは3月中旬までにもう一度行いましょう。
(3)湿害対策
これまで乾燥に経過してきましたが、3月からは降水量も平年並~やや多いと予想されています。茎立ち以降の湿害は収量と品質の低下に直接影響を与えることから、排水用の明渠をもう一度点検し、湿害を回避しましょう。
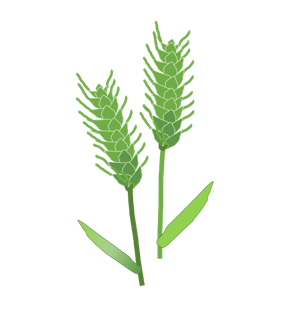
稲作の準備 (2025年3月5日作成)
1.今年の夏も猛暑の予想
最近10年の夏の気象は、2019年を除き平年よりも高く、特に昨年、一昨年は平年よりも1.8℃も高温でした。2月25日に発表された今年の暖候期(6~8月)予報では、太平洋高気圧とチベット高気圧の張り出しがともに強く、気温の高い確率は70%と予想され、今年もまた猛暑になる見込みです。
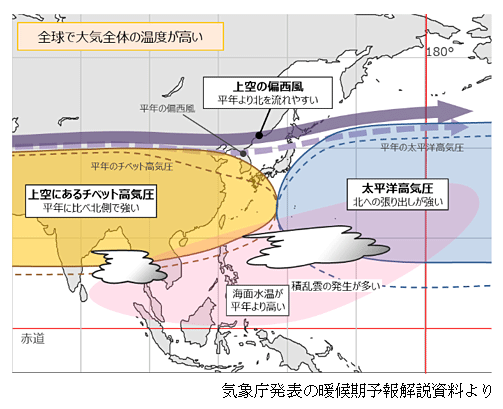
2.猛暑に備えた稲作準備
上記の特性を踏まえた栽培方法は以下のとおりです。
(1)堆肥など有機物の投入による土づくり
牛糞堆肥など粗大有機物の多い堆肥の施用は、土の団粒構造を発達させ、土壌中の有用微生物の活性を高めることなどで、稲の根の発達を促すとともに活力を高め、猛暑などのへの稲の抵抗力を高めてくれます。
牛ふん堆肥であれば10aあたり1tを目安に毎年施用しましょう。また、散布作業が容易な土づくり資材(稲サポやレオグリーン特号など)の利用も効果的です。

(2)丈夫な苗づくり
根の発育が悪く老化した稲は、田植え後の活着も悪く、天候の影響を受け易くなります。苗の発育を悪くする主な原因は①育苗中(特に初期)の潅水過多、②育苗中の高温、③育苗期間が長い(播種が早すぎる)ことが挙げられます。
毎年の作業をもう一度見直して、根張りの良い健康な苗を育てましょう。
①育苗中の潅水過多:特に緑化期に水をやりすぎると根の発達を悪くします。晴天でもよほどのことがない限り、苗箱への潅水は一日1回朝だけにしましょう。
②育苗中の温度管理:4月になると晴天日には閉め切った育苗ハウス内は高温になり、苗の徒長、むれ苗や苗焼けなどの障害が出やすくなります。最低気温が5℃以上になる3月末からは育苗ハウスの換気を行い、プール育苗の場合は原則、昼夜ともハウスの裾は開けておきましょう。
③育苗期間:稲は2葉までは自分の籾(胚乳)の養分で育つことができるので、稚苗用培土には肥料分が少ししか入っていません。稚苗(2~2.5葉)は播種からおよそ20日で完成しますが、それ以上長く育苗すると苗は栄養不足で老化し、田植え後の活着が悪くなります。種まきは田植えの20日前を目安に作業計画を立てましょう。

(3)畦畔の補修
必要な時にしっかり水を貯められることは、高温被害回避に有効です。植え代前までに畦畔の補修を行いましょう。なお、土畦畔では近年アメリカザリガニの巣穴による漏水が顕著に見られますので、被害の大きなほ場では石灰窒素を利用して駆除を行いましょう。