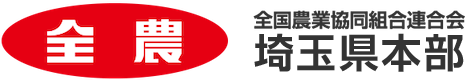営農についての情報
麦 麦類赤かび病によるカビ毒の発生に注意 (2025年6月5日作成)
今年は、赤かび病胞子の飛散好適日が例年よりも多く、特に11月下旬以降に播種した小麦が感染しやすい条件となり、発病している穂も散見されています。
5月の気温が概ね平年並みであったことから、昨年よりも今年は収穫時期が遅れており、梅雨入りと重なってくることが予想されます。赤かび病によるカビ毒の発生を防ぐため次のことを確実に実施し、被害を防ぎましょう。
1.天気予報を細かに確認して適期収穫を行い、刈り遅れを防止します。
2.倒伏等で赤かびの感染が確認されたほ場は、必ず刈り分けを行います。
3.刈り取った麦は滞留させず、速やかに乾燥施設に搬入します。
4.規定の網目を使用し、丁寧な調製作業を行います。

水稲 斑点米カメムシ防除と高温対策の徹底 (2025年6月5日作成)
(1)気象経過と稲の生育状況
4月は、月平均では気温が高かったものの寒暖の変化が大きく、早期栽培の育苗で苗立枯病の発生がやや多く見られました。5月は中旬がやや高かったものの、晴れは続かず平年よりも曇天が多く日照がやや少なくなりました。
このため、稲の葉はやや細く、軟弱気味になっているほ場も見られますが、強風による激しい植え痛みや、高温による目立ったワキの発生はなく、全般的には概ね良好な生育となっています。
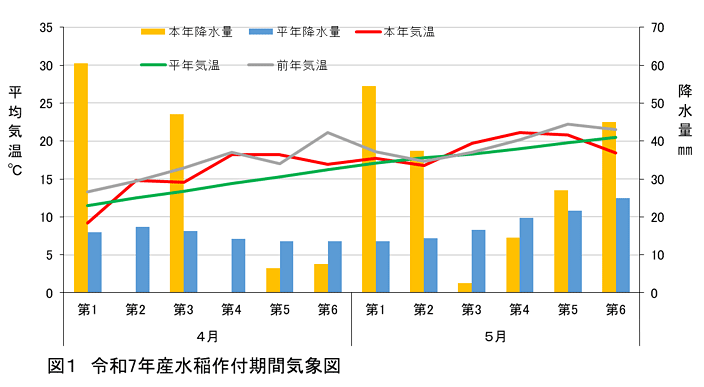
(2)今年の夏の気象予報
6月5日発表の1か月予報によれば、6月は気温は高く、曇りや雨の日が多く降水量はやや多いと予想されています。梅雨入りは、沖縄よりも九州南部が先に入るなどおかしな天候になっていますが、関東地域は平年並みと予想されています。
また、3か月予報では偏西風が平年よりもやや北の位置を流れることで高気圧の張り出しが強く、7~8月は今年も高温になると予想されます。
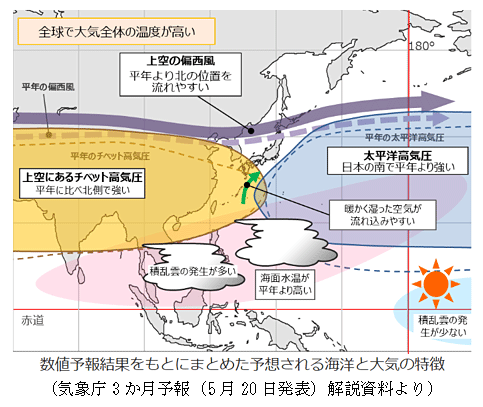
(3)稲の管理は、イネカメムシ防除と高温対策がポイント
1) 斑点米カメムシ対策
昨年猛威を振るい米の品質と作柄を低下させたイネカメムシをはじめとする斑点米カメムシ類については、越冬個体の密度も非常に高く、今年も厳重な警戒が必要です。
ポイント①
できるだけ出穂時期が揃うように品種と田植え時期を地域で揃えましょう。
周辺と出穂が違う稲には被害が集中します。また、防除も一斉にできなくなります。できるだけ地域の出穂時期が同じになるよう品種や田植え時期を工夫しましょう。
ポイント②
今の時期から畦畔や休耕田の除草を行いましょう。
畦畔などにカメムシの住み家をつくらないことが被害軽減につながります。ただし、出穂の前2週間の除草はカメムシを水田に追い込んでしまうので控えましょう。
ポイント③
田んぼの雑草防除もしっかり行いましょう。
カメムシはノビエやホタルイ等の雑草も餌にするので、田の中の除草もしっかり防除しましょう。

ポイント④
適期に薬剤防除を行いましょう。
被害の大きいイネカメムシへの防除をメインとして、1回目は「出穂期~穂揃い期」に行いましょう。これで不稔籾の発生を防ぎます。2回目は「穂揃い期の7日~10日後に行います。これで、斑点米の発生を防ぎます。

2)高温対策
高温被害を軽減するには、栽培期間全般を通じて健全な稲体を作っていく必要があります。稲の生育段階に応じた適切な管理を行いましょう。
「育苗期~田植え期」
ポイント①
根張のいい、がっちりした苗をつくりましょう。
根張りを悪くする一番の原因は水のやりすぎです。水やりは朝1回を基準にして、よほど乾かない限り日中や夕方の水やりは控えましょう。
ポイント②
活着を良くする粗めの代掻きをしましょう。
植え代は、全層を細かく掻きすぎると酸欠になって活着が悪くなります。植え代の下層は粗いままにして、上層の5cm程度を浅く二回りで仕上げましょう。
ポイント③
浅植え、薄植えにしましょう。
植え付け深さは3㎝程度、植え付け本数(掻き取り量)は3~5本程度にして、稲が窮屈しない環境をつくることで活着は早く、根張りも向上します。
ポイント④
田植え後は、浅水で管理しましょう。
田面が露出しない程度の浅水で、除草効果を保ちつつ分げつの発生を促し、がっちりした稲を作りましょう。
「本田生育期」
ポイント①
根ガス(ワキ)が発生したら一度水を落としましょう。
ガス(ワキ)は耕耘で鋤き込んだ雑草や稲株などが分解する過程で田んぼが強還元状態(ひどい酸素不足)なって発生します。このため、田の水を抜けば酸素不足が解消されガスも抑えられ、稲の生育も回復してきます。ただ、除草剤の効果が落ちますので、中期剤や後期剤で雑草対策を行いましょう。
ポイント②
中干しは適期に、適度に行いましょう。
田植え後およそ40日目頃(6月以降の田植えなら35日目頃)に7日~10日間行いましょう。これで、肥料をいったん切って無駄な分げつを抑え、新しい根を増やし、稲が穂肥を受け入れる準備を整えます。なお、田んぼの亀裂が大きくなり過ぎると、稲の根を切断して逆にダメージが大きくなるので、過度な中干しは控えましょう。

ポイント③
中干しの後からは「間断潅水」を行いましょう。
田んぼに適度な酸素を供給し根の発達を促すとともに、コンバイン走行をしやすくします。一旦入水したら水が切れるまで3~4日ほったらかし、水が切れたらまた入れる要領で穂孕みの頃まで繰り返します。
ポイント④
穂肥は適期にしっかり入れましょう。
コシヒカリは出穂の18~15日前(稲の幼穂長8~20mm程度)、そのほかの品種は出穂の20~22 日前頃(稲の幼穂長2~3㎜程度)が穂肥の適期です。稲の葉の色が濃い時は色が落ちるまで時期を遅らせましょう。逆に穂肥を入れても葉色が上がらない(濃くならない)ときは、2回目の穂肥を出穂の10日前頃(稲の幼穂長80mm程度)に施しましょう。
ポイント⑤
ケイ酸質肥料を追肥しましょう。
ケイ酸は、稲の体を固くして倒伏を防ぐとともに、光合成を高め収量向上や玄米品質低下の防止に効果があります。その吸収量は生育後半から高まるので、中干し開始時期に積極的に施用しましょう。