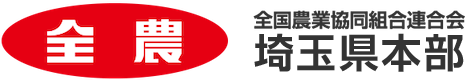営農についての情報
6、7月連続で史上最高気温を更新 水稲の生育も記録的に早くなっているため
管理作業が後追いにならないよう注意しましょう (2025年8月5日作成)
1.気象経過と今後の予報
6月中旬からの猛暑が続いています。7月の気温は前年と酷似して経過し、月平均では平年より3℃も高く、観測史上最も暑い7月となりました。また、梅雨期間中は例年よりも晴れの日が多かったものの、7月上旬のまとまった降雨により期間全体では概ね平年並みです。なお、少雨により東北や近畿・中国の地域では取水制限が実施されていますが、利根川水系、荒川水系のダムは概ね平年並みの貯水率となっています。(8月4日現在)
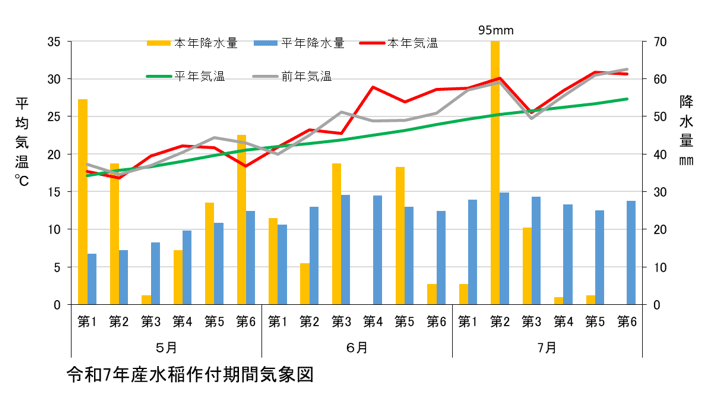
気象庁の1か月予報(7月31日発表)、3か月予報(7月22日発表)ともに、今後も気温の高い状態が続く見込みで、水稲の生育は早まり、管理作業の遅れや病害虫の多発に注意が必要です。
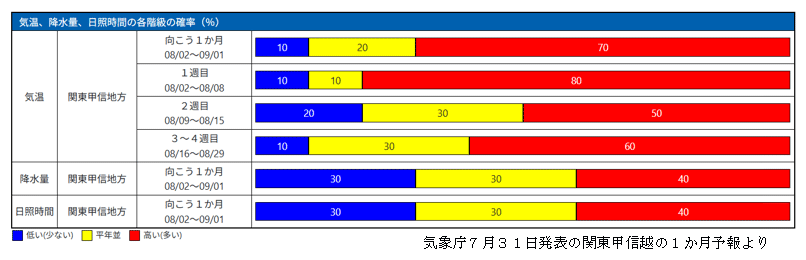
今後の生育予想と高温に対する管理
1 早期・早植栽培
1)生育と高温の影響
4月下旬から5月初旬植えの「コシヒカリ」を中心とする早期栽培と5月末までに田植えを終了した早植栽培の「コシヒカリ」「彩のきずな」等は、高温により出穂が平年よりも5日程度早くなりました。また、同時期の「彩のかがやき」も、8月5日頃から出穂が始まり、同様に早くなっています。
この早期・早植栽培では、出穂時からかなりの高温に遭遇しており、白未熟粒発生の危険度が高くなっています。さらに8月上旬の高温は玄米品質低下を助長する要因となり、登熟は促進され収穫期が早まると予想されます。
2)今後の対策
① 収穫までの水管理
田面にひたひた水が残る程度の「飽水管理」を行いましょう。
水を貯めっぱなしにするより「飽水管理」のほうが地温の上昇を抑えられます。

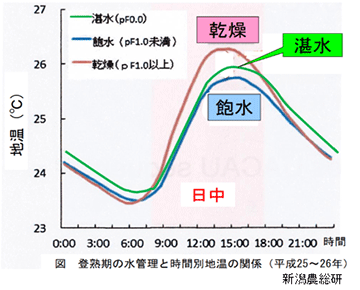
② 適期刈り取り
刈り取り時期は、出穂期からの「積算温度」で決定しましょう。平均気温が30℃を超える日が続いているため、早期・早植の稲は出穂から30日で積算温度900℃に達し、35日で1000℃を超えます。品種に関わりなく、穂の色に惑わされずに積算温度950℃からの収穫開始を準備してください。
| 出穂期 | 収穫適期 |
|---|---|
| 7月15日 | 8月16日~19日 |
| 7月20日 | 8月21日~24日 |
| 7月25日 | 8月26日~30日 |
| 8月 1日 | 9月 3日~ 7日 |
③ 斑点米カメムシ対策
県病害虫防除所から7月29日に斑点米カメムシに関する注意報が発表されました。これによるとイネカメムシ以外の斑点米カメムシも平年の4倍近く、過去10年で最も多発しています。出穂期とその後の2回防除が各地で実施されていますが、従来どおり出穂2週間を過ぎるまでは畦畔等水田回りの除草は休止しましょう。
県病害虫防除所のカメムシ注意報:令和6年度注意報第5号

2 普通栽培
1)生育と高温の影響
6月以降田植えの「彩のかがやき」「彩のきずな」とも高温で生育が促進されています。
「彩のきずな」は6月上旬植で田植え後55日程度、6月下旬植で田植え後50日程度で出穂が始まると予想され、稲の生育量が不足し穂数が少なくなることが予想されます。
「彩のかがやき」も移植期が遅くなるほど生育量が不足し、穂数の減少が危惧されます。
また、中干し実施中のほ場は乾き過ぎによる根へのダメージが心配され、葉色も落ちすぎているほ場が見られます。
2)出穂期の予測
「彩のかがやき」「彩のきずな」の田植え時期別出穂期は、以下のとおりかなり早くなると予想されます。刈り取り適期を積算温度で予想するために出穂期を必ず確認しましょう。
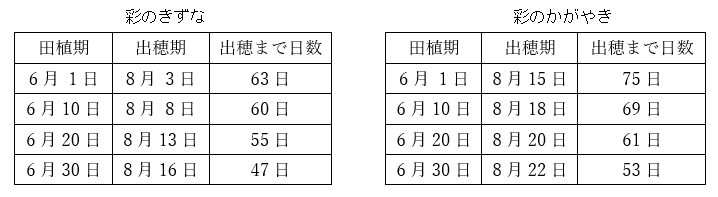
3)普通栽培の今後の対策
① 斑点米カメムシ対策
早期・早植栽培同様、イネカメムシ以外の斑点米カメムシも多発していることから、従来どおり出穂前後2週間の畦畔等の除草は避けるとともに、出穂期とその10日後の薬剤散布を確実に実施しましょう。昨年被害の少なかった地域でも、イネカメムシ以外の斑点米カメムシは多発しているのでの出穂期には薬剤防除を必ず実施しましょう。
② 紋枯病防除
高温下では紋枯病の多発も懸念されます。紋枯病の病斑が上位葉にまで進み葉の枯れ上がりが多くなると高温障害が助長され、米の品質・収量とも低下につながります。斑点米カメムシの防除とともに紋枯病の防除も徹底しましょう。

③ 穂肥を実施しても葉色が出ない場合
穂肥前の葉色が落ちすぎると、穂肥を入れたにも関わらず稲の葉色が上がらないことがあります。このようなときは、出穂の10日前頃(ほばらみ期)に2回目の穂肥を窒素成分で1~2㎏/10a程度実施してみて下さい。葉色を回復することで高温による白未熟粒の発生を少しでも抑える効果が期待できます。
④ 出穂から登熟期の水管理
早期・早植栽培と同様に、飽水管理を実施しましょう。