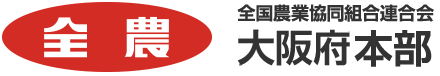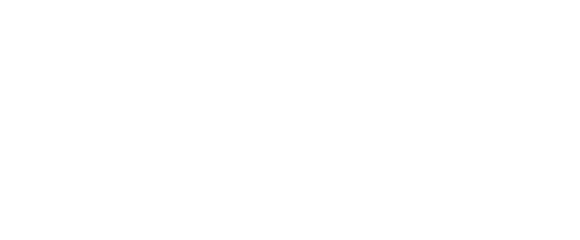【営農通信24】水稲栽培における中干しについて
水稲栽培において水管理は必要不可欠です。水管理は、ただ単に、ほ場に水を入れれば良いということではなく、栽培ステージごとにほ場の水深を適切な高さにする必要があります。今回は、7月頃に多くのほ場で行われる中干しについて説明します。
【中干しとは】
水稲栽培において広く行われている水管理作業で、分げつ(※1)期の後期に一時的に水田から水を抜いて干すことをいいます。
(※1)分げつ…水稲が枝分かれし、新しい芽が出てくること。
【中干しの効果】
1.地力チッソの水稲への供給が抑制され、過剰な分げつを抑えられます。
2.土中の有害ガス(硫化水素、メタンガスなど)の発生を抑えられます。
3.土中に酸素を供給でき、根腐れ防止や根の活力を高めることができます。
4.土を干して固くすることによって、刈り取り時の作業性を改善します。
【中干しの時期・期間】
1株あたりの茎数が約20本になった頃(田植え後約30~35日頃)、5~7日間程度行いましょう。
排水が悪く、ぬかるみの深いほ場では、中干し前か中干し開始数日後に溝切り(※2)を行って排水します。
(※2)溝切り…ほ場に溝を作り、排水溝につなげて排水を促し数m~十数mおきに、水稲の条間に深さ数㎝程度の溝を掘る作業。
中干し後は2~3回かけ流し(※3)を行い、その後、間断かん水(※4)を行いましょう。足跡に水が1cmたまる程度まで水が減少した頃、水を入れる時期の目安です。
(※3)かけ流し…ほ場の入水と出水を同時に行う作業。
(※4)間断かん水…ほ場に水を張った状態と水を抜いた状態を数日おきに、出穂15日前まで繰り返す作業。
 (写真①)
(写真①)(写真①)のように水面が見える時期が中干しの適期です。
水面が見えなくなるほど水稲が生長している場合はやや遅いです。
 (写真②)
(写真②)
中干しは、(写真②)までが限度です。
これ以上ひび割れすると根が切れてしまいますので、気を付けましょう。