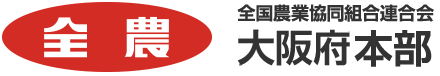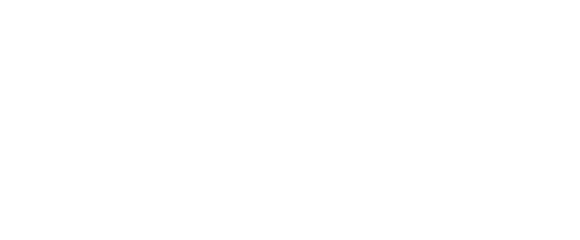【営農通信31】スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)に注意!
田植え直後の稲を食害するスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の発生に注意する必要があります。
スクミリンゴガイは南米原産の外来種で、大阪府内で毎年分布域を広げ、被害を拡大させています。越冬は可能ですが、寒さには比較的弱く、越冬率は余り高くありません。
しかし、暖冬年には越冬率が上がるため、今年は例年よりも発生が多くなる可能性があると考えられます。
1:特徴
・南米ラプラタ川流域原産で、日本産のタニシ類とは全く違う種類です。
(日本産のタニシ類は、稲や雑草を食べることはなく、藻類等をえさにしています。また、卵胎生で、卵は産みません。)
・スクミリンゴガイは1981年から食用を目的に日本へ導入されましたが、日本では定着せず、その後放置されて各地に広がり、水稲等で被害が発生しています。
今では、関東以西のほぼ全域に発生が広がっています(一部日本海側を除く)。
・大阪府では、北部・南河内の一部を除き、ほとんどの市・町に発生が広がっています。
・水稲の株や水路の壁などに、毒々しい卵が産み付けられているのを見かけます。卵には毒が含まれていますので、素手では触れないなどの注意が必要です。
2 :被害の特徴
・田植直後の稲が柔らかい時期だけ(田植後約20日間)食害が可能で、稲が固くなると食害されません。
・深水で被害が大きくなります。水中にあるものしか食べることができません。
3:対策
・冬の間に耕うんして、土中で越冬している貝を地表に出して寒さに当てたり、粉砕したりします。
・水路からの侵入防止のために、ネット等を張ります。
・田植後、浅水管理にすると活動が不活発になり、食害が少なくなります。
・卵は水中では孵化できないので、水中に落とします。(孵化直前の卵は孵化できる状態になっているので除く)
・薬剤による防除は以下のとおりです。

オススメ農薬「スクミノン」
農林水産省のホームページに、特徴・対策の詳細な情報が掲載されています。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/siryou2/sukumi/sukumi.html
これらの情報を参考にして、適切な対策に努めてください。