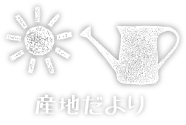農業に惹かれて

夏野菜のひとつ「にら」は古事記や日本書紀にも登場する長い歴史をもつ作物です。茨城県での生産量は全国3位。そのなかでも大きな産地の1つが水戸市にあります。
JA水戸園芸部会にら部の生産者、山﨑さんは13年ほど前に会社を退職して、義実家の農業を継ぎました。義父は水戸地区で50年以上「にら」を栽培しているベテラン生産者で、にら部の部長を勤めていました。
「日々真剣に栽培に取り組む義両親の姿を見て、農業に惹かれました。就農してみたいと義両親に相談したところ快く背中を押してくれました。私の実家は稲作農家のため、農機具の操作は慣れていたのですが、畑作は作業がまったく違い、慣れるまでにかなり時間を要しました。特に1束110gに分けたにらをJAのシールで束ねる仕事が手際よくできず、しばらく悩んだことがありました。シールは下から5cmと巻きつける場所が決まっているのですが、きつめにまかないと解けてしまい力加減が難しいのです。義両親はさっと手際よく束ねているように見えましたが、長年の経験で得た技術なのでしょう。必死に見よう見まねで勉強し、半年以上経ってやっと満足行く巻き方ができるようになりました。」と山﨑さん。3年前から栽培を任せてもらえるようになり、今では山﨑さんの名前で出荷しています。

肉厚で美味しいゼロ番

部会員は現在29名。11月~4月は寒さに強い「冬にら」、5月からは「夏にら」と露地とハウスで季節に合った品種を使い分けながら周年で出荷しています。昨年度の出荷数は全体で31,908ケース。今年度は38,100ケースを目標にしています。
「にら」は生育が旺盛で刈ってもしばらくすると再び生えてくるため、1年で数回収穫することができます。刈った順番に1番、2番と番号で呼ばれ、特に冬の寒さに耐えながら育ち、最初に収穫した「にら」はゼロ番といい、葉が広く肉厚で甘みがあり一番美味しいといいます。部会ではこのゼロ番から出荷がはじまります。

また厳しい選別基準が設けられており、切り口から葉先までの高さが38cmから45cmまで、葉幅が8cm以下で肉厚か、色合いは鮮やかであるかで等級が変わります。
山﨑さんが作った「にら」は一番良い等級であるA級品がほとんどでJAの職員さんも太鼓判を押すほどです。
デリケートな「にら」
生育旺盛な「にら」ですが、意外にも暑さや湿気には弱いというデリケートな一面をもっています。雨が降ったあと急に晴れてきた時や昼夜の気温変化の影響で、ハウス内に熱がこもり、葉先に白い縁が付く葉焼けや、場合によっては全体がとろけてしまうことがあるそうです。
常に天気予報を確認し天候が変わったらすぐに換気に行き、日々病気の発生の有無や生育状況を確認することが大切だそうです。
また、「にら」のあとにネギやニンジン、キャベツなど別の品目を栽培し連作障害を防ぐように気をつけているそうです。
農業の未来を見据えて
山﨑さんは平成29年からJA水戸青年部の委員長を勤めています。
青年部として、後継者支援や地域活性化のイベント活動、子供たちへの食育体験といった農業を通したさまざまな活動をおこなっています。
最近では水戸市内の各学校に赴き、野菜博士として授業を通して子供たちが育てているミニトマトやさつまいもなどの生育に関するアドバイスをおこなっています。
「手入れや病気について子供たちは真剣に質問してきます。授業を通して作物を育てる楽しさ、大変さを学び、将来農業を志す子供が現れてくれたらと願っています。」

山﨑さんにとってにら栽培とはどのようなものなのかお聞きしたところ、「にら栽培は子供を育てることと似ています。愛情を注げば注いだ分だけ良く育ってくれます。親として立派に育てて外に送り出してやりたい。だからこそすべて収穫することをモットーに日々勉強しています。いずれは、栽培数を増やして柔甘ねぎのようにブランド化にも取り組んで行きたいと思っています。」と照れながら答えてくれました。
生産者ならではのオススメの食べ方は、ざく切りにしたにらをフライパンで軽く炒めて納豆に混ぜる「にら納豆」。にら本来の香りが食欲を刺激するそうです。山﨑さんのお宅の定番メニューの1つといいます。
冬の寒さをじっと耐え、甘みと旨味をたっぷりと溜め込んだJA水戸の「にら」を、ぜひお召し上がり下さい。

取材協力
JA水戸 予冷センター
〒311-4155 茨城県水戸市飯島町1309-4
- TEL :
- 029-252-2525
- FAX :
- 029-255-5116