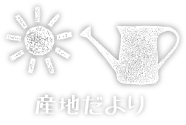米どころで始まったなす栽培

稲敷市と河内町は都心から約50km、成田空港まで約20kmの距離にある千葉県と利根川を隔てた茨城県南端の県境の町です。
かつては利根川の決壊により水害に幾度も苦しめられた歴史がありますが、水運の発展と護岸の発達により今では肥沃な土壌と豊富な水源を活かした県内有数の穀倉地帯となっています。
そんな2つの町を管轄とするJA稲敷なす部会は、県内でも貴重な作型で秋から翌年の初夏にかけて、越冬して出荷をおこなう「かわちなす」の産地です。なすは大きいほど美味しいと言われますが、成長に従い種も大粒になり皮も固くなります。しかし、かわちなすは実が成長しても種は小さく、皮は薄くてやわらかなままといいことずくめ。煮てよし、揚げてよし、炒めてよしと料理を選ばず美味しく味わえる万能なすです。
部会は個々になす栽培に取り組んできた生産者3名により、平成9年に設立されました。部会員は現在7名に増え、総面積1.3haで「かわちなす」を栽培しています。「有機にこだわった土作り」を第一に全員がエコファーマーの資格を取得している少数精鋭の部会です。また、生産者同士が集まり、出荷始めから終わりまで毎月目揃え会を開催するなど、厳しい品質基準を維持し高品質ななす栽培に取り組んでいます。

なす栽培のきっかけは

JA稲敷なす部会長の坂本さんが「かわちなす」の栽培を始めたのは今から20年前のこと。当時地元の企業を退職し、家業の米作りとともに新たな作物を取り入れた専業農家として第二の人生を歩むことを考えていた坂本さんは、以前から知り合いであったなす部会の創立者から栽培を勧められたことを機に、陸稲の圃場をハウスに変えて栽培をはじめました。「顔なじみの方が勧めてくれたので新規参入に対する安心感があったことや県や国の補助制度を利用できたことが後押しになりました。部会加入後は部会員や県内外のベテラン生産者から教えていただき、少しずつ技術を磨くことができました。」
自然のいいものだけを使った土作り

土作りは稲作地域の地の利を活かした材料を使っています。
稲刈り後に大量にでる籾殻に稲わらや糠にカニ殻や油かす、おからを混ぜて発酵させた有機質の完熟堆肥を使い、環境に優しい農業を心がけています。「社会環境やライフスタイルの変化により、安心安全な食を求める消費者の意識も高まっています。自然のいいものだけを使うことで、美味しくてなおかつ消費者に安心して食べていただけるものを作っています。」と坂本さん。
坂本さんの堆肥置き場には、近隣の稲作農家さんの家から大きなパイプが繋がっており、毎年秋口にはパイプを通して籾殻が集まってくるそうです。
また、6月末の収穫後には疲弊した土壌を回復させるため、自分たちで作って熟した良質な堆肥と発熱剤としてフスマを圃場にすきこみ、たっぷり灌水をしてその上からビニールで覆い太陽光を使った土壌消毒をおこなっています。1か月間ハウスを密閉し太陽熱で地中の病虫害を駆除し、次回のための地力を回復させています。
有益昆虫の活用

坂本さんの圃場では、暖かくなってきた3月頃からミツバチを使った受粉をおこなっています。花にぶら下がり、ゆすることで花粉をお腹におとして集めます。効率よく受粉してくれるので、受粉をして萎んだ花を取る花ぬきの作業が省け、また病原菌の発生もおさえる効果があります。

ほかにも、病気を蔓延させるコナジラミを食べる天敵昆虫を圃場に放つことで農薬に頼らない安全な栽培をおこなっています。
若い世代に託す未来
「結成当時に比べて人数は増えましたが、生産者がもっと増えてくれることが今後の課題です。部会設立当初からパソコンに詳しい会員が部会のホームページを立ち上げて「かわちなす」のPRをしてくれていましたが、今は健康上の理由によりお休みしている状態です。
私の息子も部会に入り近所でかわちなすを栽培しているのですが、これから先は息子や若い方にIT技術を駆使したPRはもちろん、栽培でもさらなる品質向上を目指して良い方向に引っ張っていってくれることを願っています。」と坂本さん。
ちなみに坂本さんのお宅では、さまざまななす料理が食卓に並ぶそうですが、特になすのグラタンがご家族に好評とのことです。
レシピは部会のホームページにも掲載されていますので、生産者おすすめの料理をぜひ味わってみてくださいね。

取材協力
JA稲敷 東部支店
〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3221-2
- TEL :
- 0299-78-2141
- FAX :
- 0299-78-2876