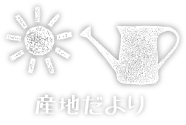そら豆の隠れた名産地

茨城県はそら豆の収穫量が全国3位を誇り、鹿児島県・千葉県・茨城県の3県で国内出荷量の6割程度をしめています。JA新ひたち野では平成27年頃からそら豆の栽培がはじまり、現在は38名の生産者で首都圏への出荷を支えています。

以前は会社勤めをしながらも兼業農家として米作りをされていた米倉さんは、定年退職を機に周りの農家さんからの勧めで約6年前に就農し、そら豆の栽培をはじめました。現在は奥さまと2人でそら豆のほか、ねぎと米を栽培しています。就農当時、畑作の経験がなかった米倉さんは講習会などの参加だけでなく、積極的に周囲の生産者とコミュニケーションを図り、一代で知識や経験を蓄えて立派なそら豆を昨年は約1t出荷しました。今回は米倉さんのふっくらとした緑が鮮やかなそら豆をご紹介します。
あらゆる外敵からそら豆を守る

そら豆は病害虫の被害や連作障害が起きやすい野菜で栽培に手間がかかります。
米倉さんは連作障害を防ぐため、4つの圃場を使用して4年に1度のローテーションで輪作しています。そら豆に影響しないように後作となるねぎの栽培計画にも遅れがないよう注意されています。

定植は11月中におこない、冬越しの際に霜で苗が傷まないように防風ネットで防寒・防風対策をします。収穫に近づく5月頃になると病害虫が発生しやすくなるため、害虫予防のシルバーマルチを使用し、定期的な消毒をおこないます。「手を抜くのは簡単ですが、それでは良いものはできないので大変でも毎回防風ネットやマルチを設置してそら豆を霜や風、病害虫から守っています。また、葉をまめに観察して、ダメになったものはいち早く取り除くことで被害の拡大を防ぎます。」と栽培時の工夫を教えてくれました。
こうした試練を幾度も乗り越えた先に品質の良いそら豆が実ります。
収穫時期を見逃さない

そら豆の枝は中が空洞で柔らかいため、株が倒れたり、実ったそら豆が地面につかないように周囲に支柱を立て、紐を張って誘引します。上を向いていたそら豆が重さで下向きになってきた頃にハサミで収穫をおこないます。「収穫時期を逃すとさやが白くなり出荷できなくなってしまうためよく目を配り、豆が大きくなってさやに硬さが出てきたら収穫します。鮮度が落ちると黒くなってしまうので天気予報は欠かさずチェックし、雨や気温が高すぎる時間帯は避けて収穫をおこなっています。」と収穫時のポイントを教えてくれました。

デリケートな野菜「そら豆」

収穫後は規格ごとに選別し、乾燥しないように湿らせた布をかけ風通しよい場所で保存します。箱詰めをおこない10度に保たれた予冷庫で予冷し、出荷され、翌日にはスーパーなどの店頭に並びます。米倉さんは「そら豆は収穫後も気が抜けません。保存状態が悪いとあっという間にさやが黒くなったりしてしまうので、とにかく品質を落とさないように工夫を凝らしています。」と鮮度が命のそら豆ならではの品質維持の難しさを語ります。また、今後の目標について「面積が減っても、手をかけて良い品質のそら豆を栽培したいです。人にあげるならきれいな状態のものをあげたいでしょう。」とあくなき探究心を笑顔で話してくれました。
JA新ひたち野のそら豆は5月から6月の間、首都圏へ出荷されます。
爽やかな初夏の味覚

米倉さんにおすすめのレシピを伺うと定番の塩茹でのほか、天ぷらもほくほくとしておすすめだと教えてくれました。また、そら豆を裏ごしして水羊羹にするとそら豆の風味と甘味との相性が良くおいしいそうです。
そら豆を購入される際にはさやが白くなっていない緑が濃いものを選び、そら豆は鮮度が落ちやすいためできるだけ早めにお召し上がりください。米倉さんのお宅では新鮮なうちに冷凍保存し、さまざまな料理に活用しているそうです。1年のうち5月から6月にしか出荷されない貴重なJA新ひたち野のそら豆をぜひご賞味ください。
取材協力
JA新ひたち野 三村集荷場
〒315-0048 茨城県石岡市三村6298-3
- TEL :
- 0299-26-5546
- FAX :
- 0299-26-5968