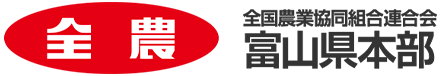「チューリップ」の栽培研究に密着!【入善高校2024⑤】
JA全農とやまでは、富山県内の頑張る農業高校生の姿をブログにて紹介しています。
今回は、富山県立入善高等学校農業科チューリップ研究班の生徒たちに密着します!
同校では、「NEW農チャレンジ事業」と称し、入善町の特産品である「チューリップ」の水耕栽培について研究しており、今年度は3年生5人と2年生3人が先生の指導のもと「チューリップ班」として活動しています。
“チューリップの大産地“である入善町では、これまで育苗ハウスを利用した土壌栽培による切り花生産が盛んにおこなわれてきましたが、土壌を消毒しても病害を回避しにくい、面積拡大が難しく生産量を上げにくいといった課題がありました。そこで、令和2年度より町内の生産者がオランダ式の水耕栽培へ切り替えを図ったところ、病害を避けられるうえ、ピントレイと呼ばれる栽培用のトレイを使用することによりハウスの回転率を上げることができ、生産量の増加へと繋がったため、同校チューリップ班でも、水耕栽培の研究に取り組むことになりました。
昨年は肥料濃度や栽植密度の違いによるチューリップの生育差についての研究をおこなわれていましたが、今年はどのような研究がおこなわれるのでしょうか。チューリップ班の皆さんを取材していきたいと思います!
昨年の研究内容はこちらから:
令和5年度「NEW農チャレンジ研究報告会」で研究成果を発表!【入善高校】 | 手しおにかける(とやまの農業をレポートするブログ) | JA全農とやま
11月上旬、チューリップの定植がおこなわれるということで、同校の上田農場へお邪魔しました。
今回は、昨年栽培した品種とは異なる「タイツブーツ」「ホワイトダイナスティ」の2品種を、水の入ったピントレイに定植していきます。

▲チューリップ班3年生による定植作業
生徒たちは、チューリップの芯がピントレイの突起に刺さらないよう気をつけながら球根を植えていきます。

▲定植完了!
最後に、定植したピントレイを冷蔵庫へ入れ保管します。

▲5℃に設定された冷蔵庫へ入れます
この冷蔵庫で2週間ほど保管したのち、約20℃のハウスへ移動し開花を待ちます。
寒いところから暖かいところへ移すことで、球根が「春が来た!」と勘違いして花を咲かせるようになります。
作業後、チューリップ班の皆さんに今年の研究テーマについて伺ったところ、
「今年の研究テーマは『バイオ炭がチューリップの水耕栽培に与える影響』についてです。バイオ炭とは、木炭や竹炭などの生物資源を原料とした土壌改良資材のことで、アルカリ性のバイオ炭を酸性土壌に用いることでPHを中性に調整するほか、様々な栄養素を植物に供給する効果があるといわれており、水耕栽培にもバイオ炭を使用すれば、チューリップの生育に変化があるのではないかと思い、『液肥のみ』と『液肥+バイオ炭』の2試験区に分けて栽培し、生育を比較することにしました。」と語ってくれました。

▲バイオ炭
そして、試験栽培を続け、迎えた12月の終わり。
同校の上田農場でおこなわれたこの日の授業では、2年生の生徒たちが、収穫適期を迎えた「タイツブーツ」を収穫し、出荷準備をしていきます。

▲ピンク色とクリーム色のバイカラーが素敵な「タイツブーツ」
先生に教わり、チューリップの茎の根元をもち、慎重にハサミをいれ1本ずつ丁寧に収穫していく生徒たち。
真剣な表情で黙々と作業を進めていきます。
 |
 |
▲収穫するチューリップを選定し収穫!
その後、収穫した1本1本のチューリップの茎と花の長さを計測し、記録用紙に記入していきます。
 |
 |
▲茎と花の長さを計測、記録
収穫した切り花の根元をカットして長さを調整し、3本ずつ透明なフィルムで包装。
全て生徒の皆さんの手作業です。

▲丁寧に包装していきます
全てのチューリップに対し、この作業を繰り返し、出荷準備の完了です。

▲出荷準備完了!
生徒たちが育てた切り花は、JAみな穂の農産物直売所などで販売する予定です。
皆さん、ぜひ生徒たちが手しおにかけたチューリップをお楽しみくださいね!
そして、気になる今回の研究テーマの検証結果については、「バイオ炭を使用した方」が、開花率・草丈の項目において生育が良いという結果になり、チューリップ班を担当している先生によると、肥料の減りが早く、養分の吸収力が高いと感じていたそうです。
 |
 |
| ▲液肥のみ | ▲液肥+バイオ炭 |
生徒に話を聞いたところ、
「栽培中は、炭を入れることで本当に生育が良くなるのかと心配だったが、良く成長して驚いたし、無事に開花してとても嬉しい。色も形も綺麗な花をお客さんにお届けしたい。」と話してくれました。
なお、今回の研究結果の詳細については、1月下旬に開催される「NEW農チャレンジ報告会」にて生徒たちが町民、生産者へ向け発表します。
次回は、その「NEW農チャレンジ報告会」で生徒たちが頑張る様子をお届けします!
JA全農とやまでは、引き続き、がんばる農業高校生を応援していきます。