米穀事業
日本人の主食である「お米」を安定して消費者のみなさまにお届けすると同時に、
生産者の所得の確保、向上を目指しています。
生産者と実需者を結び付け、
安定したお米の取引をめざす
米穀事業では、パールライス卸などの米卸売業者、米加工メーカー・外食・量販店等の実需者をつうじて、生産者から販売・委託されたお米を消費者の皆さまへお届けしています。また、実需者のニーズをふまえた作付提案をおこない、契約栽培を拡大するなど、生産者の経営安定と実需者への安定供給に取り組んでいます。

全農が取り扱うお米の主な流通経路

事業紹介
米穀事業
全農が米穀事業で取り扱うお米は、「ごはん」として食べられる主食用米だけでなく、日本酒造りに使われる酒造用米や、包装もち・菓子などに使われるもち米、米粉用米、家畜の飼料向けの飼料用米、海外への輸出用米等、多岐にわたります。こうしたお米を生産者からJAをつうじて集荷し、米加工メーカーや米卸・外食・量販店等の実需者へ供給しています。
生産者の水田営農の安定と実需者への安定供給に向けて、販売面では複数年契約や播種前契約など安定的な取引の拡大や、実需者への直接販売の拡大に取り組んでいます。集荷面では従来の委託販売に加えて、地域の実情に応じた買取の拡大にも取り組んでいます。また、近年、中食・外食等向けの需要が高まっていることを受け、実需者のニーズをふまえた、収量の多い多収米を中心としたお米の作付を生産者に提案し、技術的な支援とともに契約栽培の拡大をすすめています。さらに生産者・実需者のそれぞれのニーズをふまえた品種の開発にも取り組んでいます。
お米の需要は人口減、高齢化、食生活の変化などによって、長期的には減少傾向にあります。全農では、よりお米に関心を持っていただき、国産米の消費拡大につなげるための取り組みをおこなっています。その一環として、2022年から、多種多様な企業・団体等とともに持続可能な循環型社会の実現に向けて協働するプロジェクト「おコメ食べて笑おう」を企画・始動しています。当プロジェクトでは、「おコメ」をテーマとした取り組みや一次産業や地域社会を支えるプログラムを展開していきます。
パールライス事業(精米販売機能)
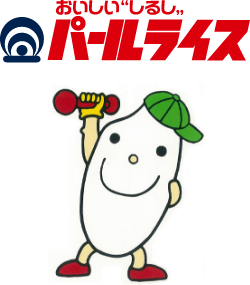
マスコットキャラクター 「パールちゃん」
全農グループは、全国各地に精米工場を設置し、お客様へ精米をお届けしています。
「パールライス」とは、全農グループ等の精米商品の統一ブランドで、2023年に50周年を迎えました。全農グループの精米工場は、「パールライス」の基本理念である「安全」「安心」「新鮮」「良品質」にもとづいて、日々、精米商品の製造に取り組んでいます。
また、全農グループでは、大消費地を中心に中食・外食業者のニーズに応えるため炊飯工場を設置し、炊飯米(白飯、酢飯など)の販売もおこなっています。
- パールライスグループ卸の一覧
-
卸名をクリックするとそれぞれのホームページを見ることができます
- ホクレン農業協同組合連合会
- 全農 青森県本部
- 株式会社純情米いわて
- 株式会社パールライス宮城
- 全農 秋田県本部
- 株式会社全農ライフサポート山形
- 全農 茨城県本部
- 全農パールライス株式会社
- 株式会社マイパール長野
- 株式会社JAライフ富山
- 株式会社米心石川
- 静岡県経済農業協同組合連合会
- 愛知県経済農業協同組合連合会
- 全農 三重県本部
- 福井パールライス株式会社
- 株式会社パールライス滋賀
- 和歌山県農業協同組合連合会
- 株式会社JAアグリ島根
- 全農 広島県本部
- 山口農協直販株式会社
- 全農 徳島県本部
- 香川県農業協同組合
- 株式会社ひめライス
- 高知県農業協同組合
- 株式会社JA食糧さが
- 熊本パールライス株式会社
- 株式会社JA ARUniCo
- 鹿児島パールライス株式会社
パールライスグループ卸の工場一覧は以下のとおりとなります。(2025年8月時点)

取り組み
実需者への出資
全農は、パックごはんの市場成長性およびお米の輸出拡大の観点から、2021年4月にJA加美よつばラドファ(現:JA全農ラドファ(株))の経営権を取得し、パックごはん市場に参入しました。 2023年11月にはJA全農ラドファ(株)「東北工場」を竣工し、生産体制を強化しました。
加えて「農協ごはん」「農協ごはん発芽玄米」「カレー専用極めごはん」といった商品開発にも取り組んでいます。
全農グループは、パックごはんの販売を通じて、国産米の消費拡大を促進するとともに、生産者の営農の安定をはかっていきます。

物流改善による輸送合理化
米穀の輸送力を確保するため、全農統一フレキシブルコンテナの拡大、紙袋輸送のパレチゼーション化を進めています。令和6年産では統一フレキシブルコンテナ53万枚(令和5年産41万枚)を導入し、パレット輸送は30県以上に拡大しています。また、物流の「2024年問題」に対応すべく、米専用列車の定期運行や異業種会社との共同輸送を実施しております。今後はフレキシブルコンテナの全国統一化と紙袋の8割のパレット輸送を目指し、米穀輸送の安定的かつ省力化によりコスト抑制を通じて持続可能な稲作経営に貢献していきます。

「おコメ食べて笑おう」プロジェクトへの参画
2022年12月、全農は多種多様な企業・団体等に声をかけ、持続可能な循環型社会の実現に向けて協働するプロジェクト「おコメ食べて笑おう」を発足しました。参加企業・団体等をさらに募りながら「おコメ」をテーマとした取り組みや一次産業や地域社会を支えるプログラムを展開していきます。

